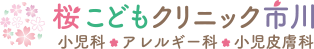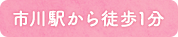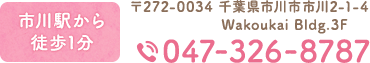赤ちゃんの頭の形について相談を受けることが多いので、こちらの文章を参考にされてください。
赤ちゃんの頭蓋骨は非常に柔らかく、頭蓋骨同士に大きなスキマが2か所(大泉門と小泉門)があり、成長に伴って形が変わりやすいです。
特に生後数か月までは頭の形が歪みやすく、頭蓋変形を起こしやすい時期となります。
まず、生後14日から生後1か月でのチェックと生後2か月ごろでのチェックがおすすめです。
3-4か月健診時では治療の開始時期が遅くなってしまう可能性があるため、心配な方はまずは当院で診察を受けてください。
赤ちゃんが分娩施設を退院して自宅に戻ったら、「タミータイム」がすすめられています。
このタミータイムは、赤ちゃんの機嫌がいい時に、腹ばいにして遊ばせる時間のことで、いわゆる「腹ばい練習」のことです。
最初は10秒程度からでもいいため、1日2-3回慣らしていくのがポイントです。
その後慣れてきたら、3-5分に増やしていきます。この時に、必ず親が常に見守っている必要があります。
毛布や柔らかいぬいぐるみなどは顔や首周りには置かないようにしてください。窒息に繋がってしまう可能性があります。
赤ちゃんが腹ばいになっている時に、親の顔が見えるといいので、親御さんも一緒に横になって遊んでみるのもいいですね。
うつぶせの時間をつくることで、成長に伴って首や背中の筋力アップにも繋がるようです。
そのため、赤ちゃんを同じ姿勢のままにせず、意識して頭の向きを変えてみましょう。
うつぶせ寝は、乳幼児突然死症候群(SIDS: Sudden Infant Death Syndrome)のリスクとなりますので、寝る時などは仰向けに戻す必要があります。
そのため、タミータイムは必ず親が側で見守っている必要がありますのでご注意ください。
頭蓋変形には、向き癖や出産時の状況が原因となる位置的頭蓋変形が多いですが、特に出産時に新生児集中治療室で入院されていた場合、筋緊張低下や先天的筋性斜頸がある場合には尚更発症しやすくなります。
その他、下記のような様々な疾患が隠れていることがあるため、小児科医の診察は必要になります。
例)筋性斜頸、頭蓋内圧亢進症、頭蓋縫合早期癒合症、大泉門早期閉鎖症、頭蓋ろう(ビタミンD欠乏)など
現時点では、頭蓋変形の重症度に応じて治療介入が必要かどうかを判断していくことになります。
当院ではヘルメット治療を導入していないため、まずは小児科医としての診察を行います。
重症度に応じて紹介が必要になりますが、ヘルメット治療をするかどうかは、専門家の御意見と治療方針を総合して、ご家族で納得できる着地点を見つけてください。
そのための手助けとして、ご心配がありましたら当院を受診してください。
ヘルメット治療の流れ
CTや3Dスキャンで赤ちゃんの頭の形を測定して、その子の頭に合ったヘルメットを作成するところから始まります。
自費治療となりますので、費用はそれぞれの施設によって差がありますので実際にお問合せしてください。(約30~50万円)
ヘルメットは、入浴時以外は1日中(23時間以上)被ることで治療効果が得られるものになるため、頭皮に湿疹ができやすくなります。こまめに皮膚の状態を観察する必要があります。また、サイズについては1週間毎に微調整していきます。ヘルメット治療を正しく行えば、非侵襲的で安全な治療法になり得ますが、全ての人に治療効果が期待できるものではないようです。
ヘルメット治療をご希望の方は、東京歯科大学市川総合病院や行徳総合病院に紹介しています。また、都内医療機関へも紹介いたします。
生後6か月以上になると治療適応から外れることもありますので、気になる方は早めに受診してください。
赤ちゃんが産まれてから、心配事が尽きることはありません。
成長発達やその他病気のこと、育児のこと、母乳のこと、離乳食のこと等、健康のことでお困りでしたらどうぞお気軽に相談してください。