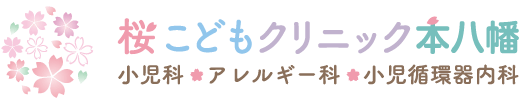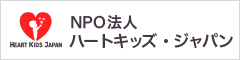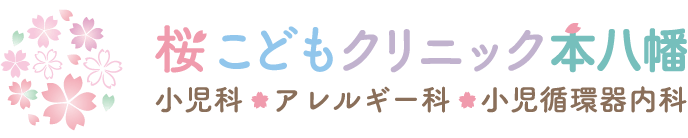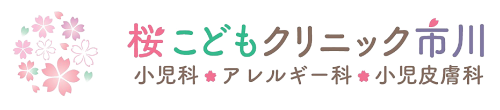夜尿症とは

夜尿症とは、おねしょのことを指します。夜中睡眠中に無意識に尿を漏らしてしまう病気を夜尿症と言います。
赤ちゃんから2~3歳頃までは、排尿習慣が未熟なため、睡眠中でも無意識にお漏らしをしてしまいます。これらの年齢のお子様がするおねしょは、夜尿症とは呼びません。
夜尿症は、5歳以上の子どもで、1カ月に1回以上のお漏らしが3カ月以上続く場合に診断されます。だいたい、5~15歳のお子様のうち、16人に1人が夜尿症だとされています。さらに、5歳では6~7人に1人、10歳では20人に1人、15歳では100人に1人が夜尿症とされています。ごく稀に、大人になるまで夜尿症が続くケースもあります。夜尿症は、年齢が上がるにつれて自然に治癒することが多い反面、学齢期になるとコンプレックスや自分への自信喪失など心理面への悪影響が及ぼされる、悩みが深い疾患です。
また、海外のデータでは、8~16歳の夜尿症では、強い精神的外傷(両親の離別や争いなど)が主な原因の第3位と報告されています。夜尿症かも?と気になる症状がある場合は、なるべく早めに医療機関に相談してください。
原因
夜尿症の原因は、大きく以下の2つが挙げられます。
- 寝ている間に大量に尿が生成される
- 寝ている間の膀胱が小さくて尿を溜められない
また、遺伝的要因も考えられ、両親に夜尿症の既往がある場合は、75%の確率でその子どもが夜尿症になるとされています。また、昼間の失禁や発育異常・慢性便秘・便失禁がある場合、夜尿症ではなく失禁の疑いがあります。
治療のタイミング
夜尿症における治療のタイミングは、年齢とおねしょの回数によって決められます。
当院では院内勉強会を定期的に行っており、小児科医と看護師と協力して治療にあたっています。
| 毎晩 | 半分程度/週 | 1~2回/週 | |
|---|---|---|---|
| 年中・年長さん | 生活習慣の見直し | 経過観察 | 経過観察 |
| 小学1~2年生 | 治療開始 | 生活習慣の見直し | 生活習慣の見直し |
| OR治療開始 | |||
| 小学3年生以上 | 治療開始 | 治療開始 | 治療開始 |
治療方法
治療の原則
夜尿症は、これまでの育て方や子どもの性格に関係なく発症する病気です。ありがちな精神論や根性論に当てはめることなく、全く別にして治療を開始していきます。
夜尿症は、お子様本人だけではなく親御さんの焦りや心配など、心身への影響が非常に大きく、それらが治療の妨げとなることがあります。そこで、夜尿症の治療を開始するにあたって、「治療の原則」を念頭に置きながら、少しずつ行っていきます。
「起こさず・焦らず・怒らず・ほめる・比べない」

周囲の人に相談しにくい子どもの夜尿症は、本人や親御さんの焦りや不安など心身へ大きく影響を及ぼします。
治療にあたっては、お子様はもちろん親御さんご自身を心の中で責めたり、焦ったりしないでください。一つでも出来たことがあった日は、たくさん褒めて自信に繋げてください。
また、夜尿症の治療は子ども本人が中心です。本人の「治す」という強い意志と側でサポートする親御さんの優しさが不可欠です。
夜尿症の治療の流れ
夜尿症の治療方法や治療期間は、患者さんそれぞれ異なります。一般的な夜尿症の治療の流れは以下の通りです。
初回診察
初回診察では、尿検査と問診を行います。尿検査では、お子様の身体の状態を確認していきます。
臓器そのものの病気がないかどうか、薬物治療に適応するかどうかを調べます。
問診では、臓器そのものの病気の有無を調べます。昼の時間にお漏らしをしたり、便を漏らしたりする場合は、臓器疾患が疑われます。
生活習慣の改善・経過観察
夜尿症は、生活習慣の改善を行うことで約2~3割のお子様が症状改善できています。
この生活習慣の改善が、夜尿症の治療の基本となります。以下の点に気を付けながら、生活していきます。
- 早寝・早起き、食事時間を決めます。朝食・昼食をしっかりと摂り、夕食は就寝3時間前までに終わらせます。
- 就寝前の水分の摂り方に注意します。午後から夕食、就寝までの水分摂取をなるべく控えます。目安は夕食時から就寝までは、コップ1杯程度です。
- 塩分を摂りすぎると水分を摂り過ぎてしまいます。塩分の摂りすぎに注意します。
- 便が腸内に留まっていると、膀胱を圧迫して夜尿の原因となります。食物繊維をしっかりと摂るなど、便秘に気を付けます。
- 就寝前には必ずトイレに行きます。
- 就寝時の寒さや寝冷えに気を付けます。身体が冷えると尿がたくさん作られます。それと同時に、膀胱が縮小して夜尿に繋がります。
- 夜中はお子様が寝ているところを無理やり起こすなどしてトイレに連れていきません。就寝中に排尿する癖が付いてしまいます。
生活習慣改善リストを記載
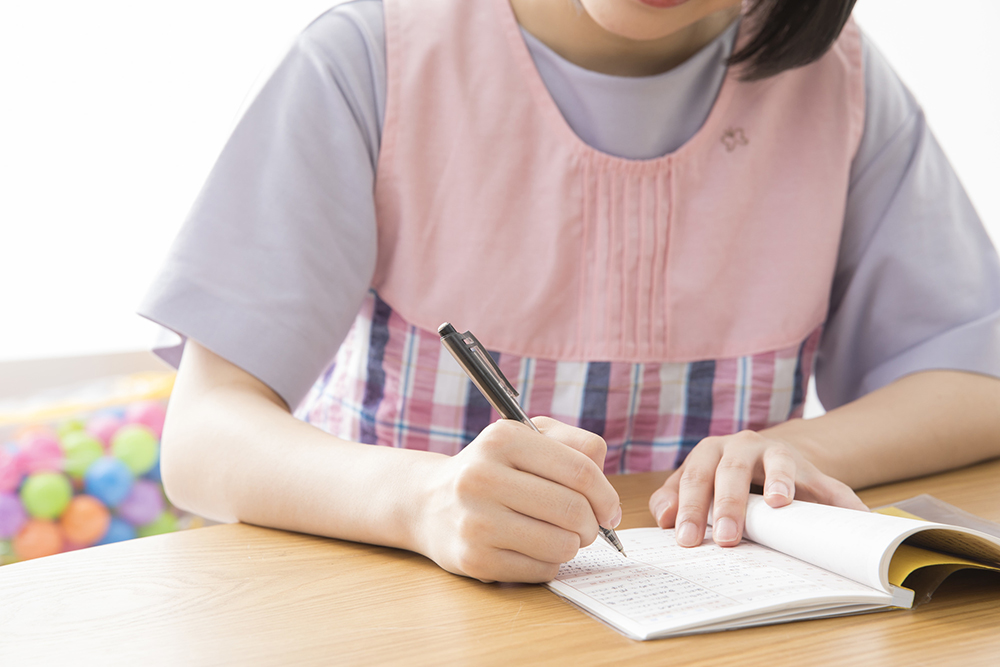
夜尿症の治療では、毎日の生活習慣改善リストを記録していきます。
日記のように、おねしょの有無を記録します。このリストを参考にしながら、診断・治療を進めていきます。
治療内容
これまでの生活習慣を改善してもなかなか症状が変化しない場合は、生活習慣改善リストをもとに、治療方法を検討していきます。
夜尿症の治療には、薬物療法とアラーム療法があります。
薬物療法
- 抗利尿ホルモン薬(内服薬・点鼻薬)
尿を濃縮することで、尿量を減らしていきます。 - 抗コリン薬(内服薬・テープ薬)
膀胱の緊張を緩和させて、膀胱の収縮を抑えることで尿を溜めやすくします。 - 三環系抗うつ薬(内服薬)
上記2つの薬物療法でも効果が見られなかった場合に、補助として使用します。
アラーム療法
パンツがお漏らしで濡れるとアラームがなる訓練方法です。おねしょをすると、すぐにアラームが鳴るため、おねしょをした瞬間を本人が認識できます。お子様のパンツにセンサーを付けて寝ることで、おねしょの回数や尿量の減少を図って、次第におねしょをする時間帯を朝方に移行させていきます。
使用するアラーム機器は、以下の通りです。
- おねしょアラームピスコール
- おねしょモニターウェットストップ3
- ちっちコール4
アラーム療法をご検討の方は、お気軽に当院までご相談ください。