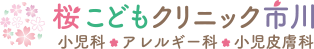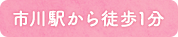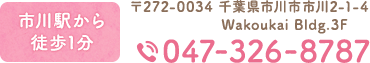こんにちは。まだまだ寒い日が続きますが、体調はいかがでしょうか?
最近、ショッピングモールで入学式用のお洋服を販売しているのを目にして、もうそんな季節に!と日々の速さに驚きました。
さて、新学期準備といえば、小児科で多く目にするようになるのが、生活管理指導表。今回はアレルギー検査の、“コンポーネント”についてお話したいと思います。
コンポーネントと聞くと、なんだか甘くて美味しそうな響きですが、リンゴの“コンポート”ではありません。笑
これまでアレルギー検査をする際、対象のたんぱく質(例えば卵白・小麦・くるみなど)の検査項目で行っています。対象のたんぱく質からアレルギーを起こす原因になりやすいたんぱく質を特定し、血液検査する方法をアレルゲンコンポーネント検査といいます。
たとえば、卵白のアレルギーの検査をする際、卵白の検査で陽性がでていても、卵白の中のオボムコイドという項目で陰性の場合、卵白を摂取できるかもしれない、ということです。
オボムコイドとは、卵アレルギーの原因となるアレルゲンであり、加熱してもアレルゲンが失われないためオボムコイドが陰性の場合は加熱卵が食べられる可能性があります。
(※1 血液検査は補助的なもので、検査結果が陽性でも、食べられることもありますし、その逆もあるのですが。)
近年、クルミアレルギーが増加しているようで、その要因は食べる機会が増えていることが影響している可能性はありますが、原因ははっきりしていません。確かに、最近のおしゃれな洋菓子などに使われていることが多いですよね。サラダに使うドレッシングにも使われていることがありますので気を付けてください。
クルミにもコンポーネントの項目があります。現在、学校や保育園でクルミを除去しているというお子さん、検査結果に、「Jugr1」という項目でも検査しているかどうか、ぜひ一度確認してみてください。他のナッツ類や大豆もコンポーネント検査のある食物ですので、見てみてください。
新学期に向けて生活管理指導表を更新するタイミングに、検査結果の用紙をお持ち頂いて、当院のアレルギー専門医にぜひご相談ください。
(スタッフR.M)